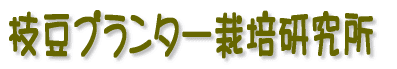大豆の主な品種とその特性
北海道の優良品種は、分類法の一つとして種皮色(主要な黄、緑、褐、黒)、粒大(小粒、中粒、大粒、極大粒)および臍色(褐、白、黄、黒)を組み合わせ14種類に分類しています。その分類による代表的な品種特性を次に示します。
黄色小粒白目種
代表品種として納豆用品種「スズヒメ(大豆十育182号、だいず農林71号:1980〜)」は、ツルマメ同様の極小粒黒豆で線虫抵抗性の「P18751」を母に、「コガネジロ」を父として育成されました。熟期は中生の早で、粒大は小(百粒重12.0g前後)、種皮色は黄、臍の色も黄。中〜大粒の品種に比べると収量は10〜20%劣ります。主要な栽培地は十勝中央部です。
同様な納豆用の小粒品種には、関東地方では晩生の早で極小粒の「納豆小粒」、中生から晩生で極小粒の「コスズ」、北海道では中生小粒の「スズマル」があります。
「納豆小粒」は金砂郷村の在来種より選抜して、1976年に茨城県農試で育成されました。熟期は関東地方では晩生、長茎で多分枝型の草型、極小粒に属し品質は良く、納豆加工適正大です。主な栽培地は茨城県です。
「コスズ(大豆東北85号、だいず農林87号:1987〜)」は、「納豆小粒」に放射線照射した突然変異種で、東北農試で育成した品種です。種皮色は黄白、臍の色も黄色で、納豆用品種として、岩手、宮城、秋田、福島、茨城などで栽培されています。
「スズマル(大豆中育19号、だいず農林89号:1988〜)」は、「十育153号」を母に、「納豆小粒」を父として育成された品種です。成熟期は10月上旬の中生種で、種皮色および臍の色が黄、粒大は小(百粒重14.5g前後)で、「スズマル」銘柄の納豆用品種です。「スズヒメ」より多収で、耐倒伏性も優れています。主要な栽培地は道央中・南部、洋蹄山麓です。
「鈴の音(大豆東北115号、農林101号:1995〜)」は、「刈系224号」を母、「コスズ」を父として東北農試で育成されました。熟期は早生、耐倒伏性が強く、コンバイン収穫適性が高い納豆用品種です。主な栽培地は岩手県です。
黄色中粒褐目種
臍色が褐色の大豆を褐目種と称し「秋田」銘柄としていますが、国内の褐目種に属するのは北海道の「キタムスメ」「北見白」「ハヤヒカリ」「キタホマレ」と、九州・四国の「フクユタカ」の5品種のみです。うち、「キタホマレ」は大粒ですが、他の4品種は中粒です。
中粒褐目の代表品種「キタムスメ(大豆十育122号、だいず農林49号:1968〜)」は、「十育87号」を母に、「北見白」を父として育成された品種です。中生種で、粒大は中(百粒重31.0g)、種皮色は黄白で、臍の色が暗褐の褐目種で、耐冷性に優れる品種です。良質、安定多収で、加工品がおいしく、納豆、豆腐、ドライビーンなどに使用されています。主要な栽培地は上川、十勝および後志地方です。
「フクユタカ(大豆九州86号、農林73号:1981〜)」は、「岡大豆」を母、「白大豆3号」を父として九州農試で育成されました。良質、多収、高たんぱく質の品種です。現在、九州、東海地方で作付が多く、平成9年には13,500haと全国一の作付面積です。
黄色中粒白目種
「トヨコマチ(大豆十育205号、だいず農林90号:1988〜)」は、耐冷性強の「樺太1号」を母に、線虫抵抗性で良質多収の「トヨスズ」を父として育成された品種です。成熟期は中生の早で、耐冷性がやや強く、低温下での臍周辺の着色粒の発生が少ない品種です。主要栽培地は十勝、網走、上川地方です。
このグループに含まれる品種に、青森、岩手の「スズカリ」、秋田の「ライデン」、東北地方の「スズユタカ」、近畿・中国地方の「タマホマレ」、九州地方の「むらゆたか」などがあります。
「スズカリ」は熟期が中〜晩生で、線虫抵抗性の多収品種、「ライデン」は放射線照射により育成された中生、線虫抵抗性品種、「スズユタカ」は1982年に東北農試で育成された中〜晩生、ウイルス病および線虫抵抗性の良質、多収品種、「タマホマレ」は1981年に長野県中信農試で育成された耐倒伏性強、多収品種、「むらゆたか」は「フクユタカ」の放射線照射により1991年に佐賀県農試で育成された良質、多収品種です。
黄色大粒褐目種
「キタホマレ(大豆十育171号、だいず農林70号:1980〜)」は、「十育114号」を母に、「カリカチ」を父として育成された耐冷性、多収の品種です。熟期は中生の晩で、粒大は大、種皮色は黄白、臍の色は暗褐です。主な栽培地は道央中部・南部です。
黄色大粒白目種
「トヨムスメ(大豆十育191号、だいず農林81号:1985〜)」は、多収で大豆黒根病抵抗性の「十系463号」を母に、良質で線虫抵抗性の「トヨスズ」を父として育成された品種です。成熟期は中生、「トヨスズ」に極めて似た草型で、種皮色および臍色が黄色の白目種で、「とよまさり」銘柄に属します。中〜大粒種(粒大は大の小)で、百粒重は32〜35g、収量は327/10a程度です。主要栽培地は十勝、石狩、空知、後志、胆振地方です。
同様な品種として、府県で広範囲に栽培されている「エンレイ」やその血を引く「オオツル」「アヤヒカリ」、関東地方の「タチナガハ」などがあります。
「エンレイ(大豆東山57号、だいず農林57号:1971〜)」は、「農林2号」を母に、「東山6号(シロメユタカ)」を父に、長野県中信農試で育成された品種です。粒大は大で、種皮色は黄、臍の色は黄の白目種で、その晩播適応性が大であることから、東北南部、関東、北陸、東海、近畿、中国と広範囲に栽培されていました。たんぱく含有量が高く、豆腐や煮豆にも向いていることから「フクユタカ」に次ぐ作付面積(平成9年・10,000ha)があります。
「オオツル(大豆東山144号、だいず農林91号:1988〜)」は「東山80号」を母に、「エンレイ」を父として交配し、長野県中信農試で育成された品種です。熟期は中生で、種皮色は黄、臍の色は黄、粒大は大で、煮豆加工適性に優れる品種です。
「アヤヒカリ(大豆東山149号、だいず農林96号:1991〜)」は、「エンレイ」を母に、「東山53号」を父として育成された品種です。熟期は中生、種皮および臍の色は黄、粒大は「エンレイ」より大で、多収です。味噌など蒸煮加工する製品に適し、豆腐加工にも向きます。
「タチナガハ(大豆東山85号、だいず農林85号:1986〜)」は、「東山61号」を母、「東山6627号」を父として長野県中信農試で育成されました。熟期は中生の晩、耐倒伏性強、線虫抵抗性の多収品種です。
黄色極大粒白目種
「ユウヅル(大豆中育3号、だいず農林55号:1971〜)」は、「鶴の子」在来種より純系分離し、育成された品種です。晩生・極大粒の白色種で「つるの子」銘柄の代表品種です。品質は極めて良好で、煮豆・総菜用のほか、豆腐、油揚げなどに利用されています。主要な栽培地は檜山南部、空知南部地方です。
「ツルムスメ(大豆中育24号、だいず農林94号:1990〜)」は、わい化病抵抗性の「中系67号」を母、大粒良質の「中育12号」を父として育成された中生白目極大粒の品種で、良質で煮豆、総菜用に利用されています。「ユウヅル」とともに、「つるの子」銘柄の品種です。
黒色大粒黒目種
「中生光黒(十支第963号:1933〜)」は、品種比較試験により、在来種(本別村産)より選抜した品種です。熟期は晩生の早で、粒大は大、種皮も臍の色も黒の黒色大粒黒目種です。多収で、良食味で煮豆用に向きます。主な産地は十勝、檜山地方です。
「トカチクロ(大豆十育184号、だいず農林80号:1984〜)」は、「十育122号」を母に、「中生光黒」を父として育成された品種です。早熟、多収の中生種で、種皮および臍の色は黒で、粒大は大。主な栽培地は十勝地方です。両品種は銘柄区分では「黒大豆(光黒)」銘柄に属する品種です。
「いわいくろ(大豆中育39号、だいず農林107号:1998〜)」は、極大粒、良質の「晩生光黒」を母、わい化病抵抗性の大粒白目系「中生21号」を父として北海道中央農試で育成されました。熟期は中生、わい化病抵抗性やや強で、極大粒の黒大豆です。煮豆加工適性は「晩生光黒」並に良好です。主な栽培地は道央、道南、十勝地方です。
「みすず黒(大豆東山黒175号、だいず農林106号:1997〜)」は、極大粒、良質の「丹波黒」を母、ウイルス病抵抗性の「東山140号」を父として長野県中信農試で育成されました。熟期は中生の早、ウイルス病抵抗性の極大粒の黒大豆です。粒大、収量ともに「信濃早生黒」(37g、330kg、平成8年)に優ります。
「丹波黒」は丹波・篠山地方の在来種です。ただし、純系分離を行って1981年に京都府農試で「新丹波黒」を育成しました。熟期は11月上旬の晩生種。茎長は中位、分枝が多く、倒伏・つる化しやすい。子実は光沢なく、ロウ質です。粒大は極めて大きく、百粒重が60g前後であるが、栽培方法によっては80gを越えることもあります。主な栽培地は近畿、中国、四国地方です。